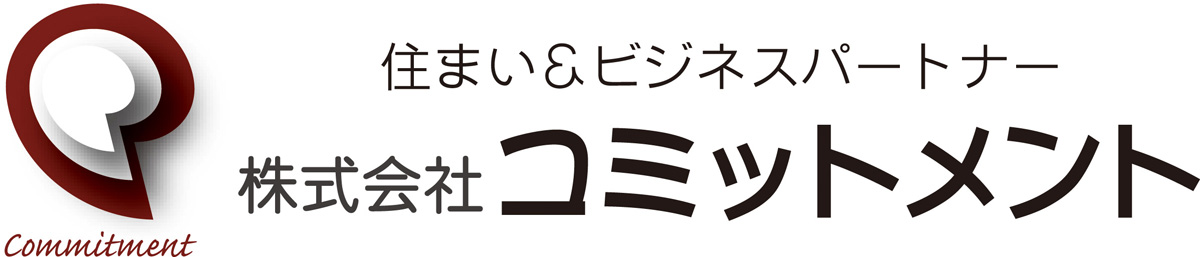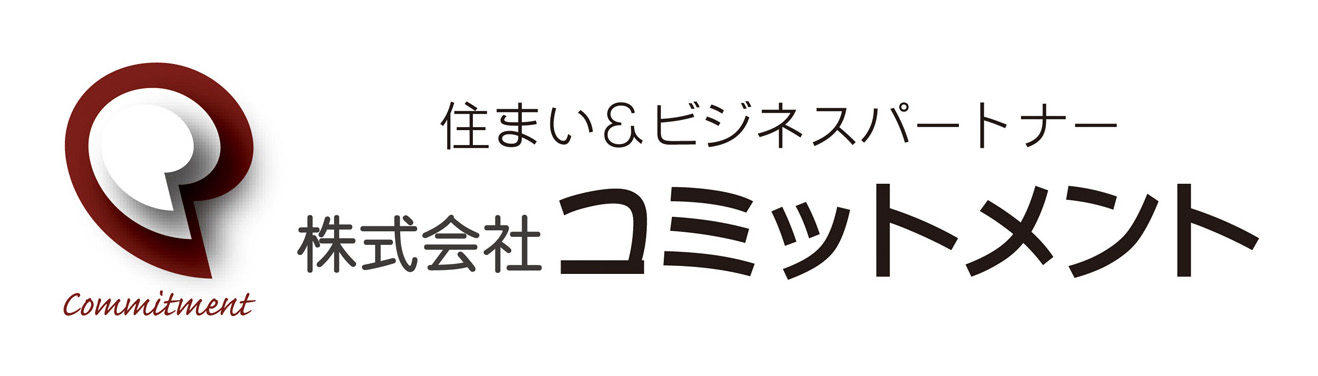【2023年コラム】
1月のコラム 2月のコラム 3月のコラム 4月のコラム
5月のコラム 6月のコラム 7月のコラム 8月のコラム
9月のコラム 10月のコラム 11月のコラム 12月のコラム
『 鯛は頭から腐る VOL236』 12月のコラム上へ
2023年も最終月。毎度のことながら今年も色んなことがありました。過ぎてしまうと忘れてしまうので、何があったと言われれば「あれ?何があったんだっけ」というくらい矢のごとく次々と何かが出てきてどんどん忘れていく。仕事、お金、健康、人間関係。尽きることなく降りかかってくる色んなこと。その都度優先順位を判断しながら、すぐ対応しなければならないことと、後回しにしてもよいことを振り分けながら何かと追われている。
年金で一人暮らしや家族がいても会話がない年配者は誰とも話さない日が多く、誰かと何でもいいのから会話をしたいそうだ。特に男性に多い。本人の心得といってしまえばそれまでなのだが、買い物と病院くらいしか外出せず、外に出ても挨拶程度で終わってしまうので、孤独感が募るとのこと。かといって何かを変えるということもせず、できず、日々を過ごす。そういうことを耳にすると色んなことがある内が花なのかもしれない。年配者は孤独を抱え、社会を支えている年代は仕事や生活に疲れ、若者は目の前の刺激の強い遊びやSNSに夢中になる。憂いても、何かをできるわけでもないが、心の荒れは短角的になっているようで切ない。
鯛は頭から腐る:語源はロシアのことわざ。魚も頭から腐るように組織も上層部から腐っていくという意味でよく知られている。政治であれ企業であれその通りで実例は枚挙にいとまがない。なぜ良くないことに手を染めるのか。厳罰化しても監査を厳しくしても後を絶たないのはなぜか。神田財務副大臣が固定資産税を滞納して差押されていたことが表沙汰になった。それも4回。それも税理士資格を持つ。こういう報道をみると範を示すべき国会議員が一体このザマは何かと空いた口が塞がらない。
この2ヵ月で柿沢未途法務副大臣が公選法違反容疑事件に関わったとして更迭。法を遵守すべき法の番人が法を犯す。さらに山田太郎文科政務次官が女性問題で更迭。これらは表に出ただけで本当は氷山の一角だ。すごい世の中になったものだ。とはいっても誰かを選ばなければならないし。このようなリーダーで国の舵取りが進んだらこの先どうなるのだろう。来年が楽しみだ。保身と権力の世界だからしょうがないのかなぁ。まともなリーダーの出現を望むことは不可能なことなのだろうか。ここはひとつ満票で2回目のMVPを獲った大リーグの大谷翔平にでもリーダーになってもらうか。ということで今年も終わり。さぁて2024年の門松をくぐるかぁ
『 アンガーマネジメント VOL235』 11月のコラム上へ
アンガーマネジメント:直訳すると「怒りの管理方法」1970年代アメリカで発祥。怒りの感情と上手に付き合っていくメソッド。当初は犯罪者の矯正プログラムとして活用されたが、最近は企業の研修などにも取り入れられ、日本でも耳にすることが多くなった。
職場や家庭や友人関係でも何かの拍子でイラついた時、うまく感情を切り替えができず、不機嫌に黙り込んだり、周囲に八つ当たりして、後で後悔したことはないだろうか。冷静に怒るべきときは怒り、怒る必要のない時は怒らない、とコントロールできればいいのだが、人間そうはなかなかいかない。物を壊したり、相手を怒鳴ったり、自分がどのような時に怒りを感じやすいかを理解することがマネジメントの一歩。そして怒りの感情をコントロールして主体的に感情を選択できるようにする。
怒りは良くない感情と捉えて、抑え込もうと考えがちだが、その反面、例えばスポーツで負けた時に悔しさや自分に対する怒りをバネにして練習に励むように、怒りは原動力となることもある。先日将棋の冠位をすべて独占し話題になった藤井聡太8冠。小学生の頃に格上の相手に負けて将棋盤を抱き抱えて周囲の目も憚らず大泣きしたという。それ程負けが悔しかったようだ。自分に対しての発奮材料としての怒りは大いに結構だ。
アンガーマネジメントが注目されるようになった背景には、社会の価値観の多様化がある。さまざまな価値観やライフスタイルを認め合う社会へと変わっていこうとする一方、自分の価値観以外を受け入れない人も多くいる。旧統一教会の現役の信者などをみていると宗教などもそれ。自分と異なる価値観を持つ人と接する機会が増えた現代では怒りを溜め込めやすい人が多くなり、ストレスが高じてその吐け口として犯罪に至る場合もある。
自分では常識だが、相手は非常識。上司は教育のつもりが部下はパワハラと感じる。高卒、大卒に関わらず離職率が以前より高い。離職サイトやエージェントがここ数年で俄然多くなった。世の流れとはいえ転職して前職より収入が上がった人は35.9%、変わらない人は28.3%(令和2年厚労省上半期雇用調査)。この数字をどうみるか各人それぞれだが、特に21世紀になってから老若男女に関係なく怒りの感情を抑えられない人、キレやすい人、自分勝手で協調性が少ない人が多くなったように思えるのは、気のせいだろうか。
『 宿命・運命 VOL234』 10月のコラム上へ
ふと自分のこれまでの生き方、人生を振り返る時。
宿命:生まれる前に決まっている。運命:生まれた後に決まる。宿命・運命の定義はこういうのが一般。生まれた場所、国、環境、時代、両親、性別などは生まれ持って決まっているので、変えることができない、受け入れざるを得ない。運命は「巡り合わせ」で自分の意思に関係なく巡ってくる幸、不幸。幸、不幸を左右することはできないが、日ごろの行いや選択の積み重ねにより変わっていく、ようだ。
高い学歴があり、財力があっても幸せを感じられない人がいる。否多いといっていいだろう。人は人との人間関係の中で生き、相手から影響を受け、又相手に影響を与えて、自分の存在を自覚し、成長していく。学歴のあるなし財力の有無などというレベルの問題ではなく、出会いと縁によって人の魂は上昇していく。例えばどの学校にするかどのような職に就くかは自分の意思で決めることができるだろうが、そこでどのような人に出会うかはまさに運。人生が動くきっかけは出会いと言っていい。
宿命、運命の他にも天命、使命もある。天命:天から与えられた命、宿命に近い。使命:ミッション。自分が何のために生まれてきたのか、何に命を使うのか。性転換など宿命が運命になる時代になった。3~4歳の幼児に「どうしてママのところに生まれてきたの」と聞くと「ママが淋しそうにしていたから」とか「ママに会いたかった」からと3割くらいの幼児が答えるそうだ。だとしたら国も場所もその他の環境も全部自分で選んできたといえる。さらにはどこで誰と会うかの「巡り合わせ」も、もしからしたら自分で選んで決めていたのかも。気づかないで意識しないで、自分で決めている未来。自分で決めていた未来。
だから何事も宿命だ運命だといって社会や人のせいにしてはいけない。どうして自分はこんな苦しい思い、嫌な思いをしなければならないのだろうと思ったら、この思いから抜け出したいと思ったら、生き方、考え方を変えろという暗示。自分に甘えず努力しろということ。振り返ってみた時その過程も自分が決めていた、時期相応に自分でセットしていたと気づく。決まっていてもその時は分からないから決まっていないのと同じともいえるが、、、生老病死、喜怒哀楽、すべて自分で選んでいた道。だから愚痴はいえない。こう考えると宿命も運命も天命も使命もすべて必然かも。すべては気づくことから始まる。
『 4万6000年からの目覚め VOL233』 9月のコラム上へ
ロシアがウクライナ侵攻を始めて1年半。研究者にとって政治的な対立は別ものらしい。ロシア・モスクワ大学とアメリカ・プリンストン大学やドイツなどの研究チームが7月に驚くべき発表をした。ロシアのシベリアにある永久凍土の堆積物のサンプルが溶けて4万6000年も眠っていた線虫が目覚めたというのだ。さらに数週間もすると、動き出して繁殖を繰り返し数千匹に増殖した。この線虫はメスしかおらず、オスがいなくても子孫を残せる単為生殖。線虫からすると目が覚めたら人間だらけの4万6000年後の世界が待っていた。
地球温暖化で北極の氷だけでなく永久凍土がどんどん溶けている。今年も台風で大きな被害が各地で起こった。日本だけでなく世界各地で洪水やハワイ・マウイ島のような大規模な山火事が発生。年々大きな自然災害が頻繁に起きている。今回の線虫は人間に害はないようだが、永久凍土が溶けることで太古の時代からそこに閉じ込められた細菌や微生物が眠りから覚める可能性がある。それが人類にとって害となる病原菌だとしたら。人間同士が争っている間に、欲望を満たそうとしている間に、目に見えない菌が人類を地球上から消し去るなんてことになるかもしれない。一部の強欲な支配者が世界を手に入れたとしても、、、気が付くころには手遅れになっている。
うだるような暑さで熱中症警戒アラートが連日発表される今夏。命の危険な暑さでエアコン使用推奨→地球温暖化が進む→永久凍土が溶ける→人類に害ある菌が生き返る→人類が滅ぶ。なぁんてことがありうるかも。各国の首脳が国際会議のため飛行機に乗り→車で移動→エアコンの効いた部屋で会議。議題は地球温暖化について。核戦争ではなく便利さの享受で自業自得。かといってエアコン止める?車使わない?飛行機乗らない?なぁんてことができるか。産業革命前に戻ることはできない。江戸時代に戻ることはできない。はてさてどうしたものか。自分のちっこい頭ではこれといった良き解決策など思い浮かびもしないが、一応懸念心は持っておこう。エアコン28℃にして。
今回の研究者達。争い合う国の垣根を超えて成果を出した。本当に訴えたいのはこうした目に見える成果で、人類の危機を為政者に感じてもらいたいのではないか。何が起こっても不思議ではない世の中。人類にとって便利な世の中は地球にとっては汚されることのようだ。人類の知能では計り知れない何かを人類は自ら引き寄せている。線虫の次は何が生き返るのだろう。それが果たして人類にとって否、地球にとってどのような影響を与えるのだろう。
『 徳と才 VOL232』 8月のコラム上へ
明(みん)の洪自誠(こうじせい):菜根譚(さいこんたん):徳は才の主(しゅ)、才は徳の奴(ど)なり。才ありて徳なきは、家に主なくして、奴の事を用(もち)うるが如し。幾(い)かん何ぞ魍魎(もうりょう)にして猖狂(しょうきょう)せざらん。
徳というのものは、その人の持って生まれた性格・雰囲気、身についているもの。それに対して頭の働き、能力等は才。この二つの要素を人間は持ち合わせている。どちらかというと、才が徳より勝っていれば小人(しょうじん)。徳が才より勝っていれば君子(くんし)。小人というと悪いように聞こえるがそうではない。大徳・大才を持っているが、大才のほうが大徳よりも優れていると大小人、偉大な小人。ケチな徳とケチな才なら、ケチはケチでも徳のほうが勝ってケチな君子となるから、一概に小人が悪い君子が良いとは言えない。さらに徳が過ぎると情に流され、お人好しになる。才が過ぎると細々とうるさい。過ぎたるは及ばざるが如しだが、どういう学問を得るかにより徳と才の出方が違う。点を取るための勉学では才が、人間学を学ぶと徳が上回る。
徳と才は両輪だが、主は徳で才は従。才能があるのに人徳が伴わないのは、主人がいない家で使用人が好き勝手に振舞っているようなものだ。これではせっかくの家も妖怪の巣窟になってしまう。よく頭が良くリーダーとして前に出たがる人が意外なミスをしたり、余計な事を口にして顰蹙を買って失笑される。学校の成績のように才は数字で見ることができるが、徳は雰囲気なので数値では出せない。勉学ができたから良い教師になれるかというとそうとは限らない。スポーツの世界で世界記録を達成したり、金メダルを多く取ったり、三冠王になった人が監督や指導者として成功することは稀である。
保険金不正請求問題で世間の関心を集めているビッグモーター。報道を見聞きする限りではかなり悪どい不正をしているようだ。利益最優先で過剰なノルマを課し達成できないと降格人事で脅かす。一代でここまで会社を大きくした社長のようだが、おそらく人格を磨くことを怠ってきたのだろう。このような不祥事で会社が存続できなくなったり、リーダーが失脚した例は後を絶たない。最初のころは悪いと分かっていたが、バレなければいいとか、だんだん麻痺してそのうちに常態化してしまう。諫言する人を遠ざけ、イエスマンを身近におき、世間が見えなくなる。まさにお山の大将。
何となく近くにいると安らぐ人がいる。いくらお金や才能や人気があっても徳が大きい人には及ばない。そういう目で人を観察していると徳人は意外と身近にいたりする。数はすくないが、、、そして自分も目指すはもちろん。
『 為さざることあり VOL231』 7月のコラム上へ
孟子・離婁(りろう)編 「人 為さざることあり。而して後、以って為すことあるなり」。人は為すべきでないことをしない。その後に為すべきことが見えてくる。為すべきことよりも為さざることが先。人間とは、自分の欲望に任せると何をするか分からない。悪知恵を働かせて何でもしでかす。SNSを使って海外から遠隔操作で実行犯を募り、殺人まで誘導して金を奪い取る。末法の世もいよいよ末に差し掛かったかと思う。
世の中がどうなるか分からないが、自分はこういうことは絶対にしないんだという気概が「為さざることあり」。これは理性と強い意志による気概を持てということ。だらしのない欲望や興味に任せた生活に締めくくりをつける。如何なる誘惑や迫害を受けても、最後に為さざるところがなければならない。得てして、甘い誘いや儲け話、又は脅迫などで人間というものは為らぬことも為してしまう。富を以ってしても、武力を以ってしても、なにものを以ってしても奪うことができない信念を持つ。この譲れない信念、芯を持っていないとブレる。他人の言動に左右される。ブレて左右される人生を送っていると振り返った時、後ろには誰もいない。
ある夫婦が遅くにやっと生まれた息子を溺愛。息子は長じるに従い我儘のし放題。すべて欲しいものは買い与えた結果、自分の欲しいものが手に入らないと暴力をふるうようになる。いよいよ金がなくなると父親に勤め先を退職して退職金をくれとまで言い出す始末。困り果てた両親は某氏に相談。高校生になっていた息子は某氏の言うことなど聞く耳を持たず、某氏は荒治療を決行。無理やり高校を退学させ、その日暮らしの飯場の建設現場に放り込む。そこでやっと放蕩息子は更生し、高校も入り直し全うな人間になった。まぁこれは数少ない成功例だろうが、多くは為さざることをきちんと幼少時から教えて諭さないとしっぺ返しがくる。
そして「而して後、以って為すことあるなり」。自分を確立させて、いざ為すことを為す。ある程度の年齢になれば自分の為すべきことが見えてくる。孔子のいう「50にして天命を知る」に通じる。日々、目の前の何事かに追われてはいるが、振り返った時自分の後ろには誰かいて欲しいものだ。どれだけの人がそういう思いを持っているだろうか。せめて自分だけでもとの思いはあるが、まだまだだなぁ。
『 もの言わぬ草木 VOL230』 6月のコラム上へ
よく百人百様というが人に限らず動物でも植物でも魚類でも自然界には同じものはない。同じ種類の花でもまるっきり同じということはない。それぞれの個性がある。特に植物は自分で移動することはできないのでその場で一生を終える。人間でいう意識というものはないのだが、それでも自分を主張している。例えば花。見る人が花に感情移入してみるのだろうが、昨日見た花と今日見る花では違うように見える時がある。話しかけてもうなずく訳でもなく、ただそこに佇んでいるだけなのに癒される。存在感を感じる。
花や木は動かないが、感情があるように感じたり雰囲気を醸し出したり、時には叱咤激励してくれるような感覚は何なのだろう。よく考えてみると意思や感情がない方が世の中丸く収まるのではないか。なまじ喜怒哀楽があるから争うことになる。文明の発展により人間は今日の世界を創り上げてきた。競争の中で人より早く強く便利に、を追い続けた結果本来の人としての姿を見失った感がある。人類のためによかれと思い一生懸命に創り出したものがあとになって有害だったなんてことは枚挙にいとまがない。気が付いた時には後戻りできない。後処理ができない状況になってしまい途方に暮れる。処理に膨大な時間と費用をかけざるを得ない。
人生の後半になると穏やかな日々を望むのは人情だが、そうは問屋が卸さない。いくつになってもそれぞれ抱えるものがある。それも一つや二つではなく、あれもこれもといくつもある。ひとつ何とかなったと思ったら新たに思いもよらない事態が起こる。ストレスの連続はなくなることはない。なくなることはないが不思議と忘れてしまう。あとで振り返りあの時は何で悩んでいたんだっけとかあんな小さなことで悩んでいたんだと思ったりする。それが人の一生ということになるのだろう。自分自身を鼓舞して自分の生き方を全うする。
風のない地平では草は育たないそうだ。水があって土壌が良くても育たない。要は草にとって風はストレス。ということは全て生きとし生けるものは適度なストレスが必要だということだ。適度なストレスというものは年齢、性別、性格によって違う。強過ぎると心が折れ自暴自棄になるし、弱ければ人間的な成長ができない自己中心的で傲慢な人間になってしまう。草はどんなに強い風でも根をしっかり張り光の方向に伸びていく。そういう思いで花を愛でると、もの言わぬ草木には見習うべきものは多いのだと改めて感じる。
『 余力を遺す VOL229』 5月のコラム上へ
政治家でもスポーツ選手でも芸能人でも、ほとんどの人が知っているいわゆる有名人。世の中の人がその人を推し尊ぶ余り、その子供が虎の威を借る狐のごとく、自分は名門の子だ、自分の親は偉いんだと、自分も偉いような気持ちになって、驕り怠ける性格になってしまう。結果有名人の子は不肖である。まぁ極端な話だが、世間にはよくあることだ。
言われてみれば確かにずーっと代々有名人が続く家があるかというと歌舞伎とか能とか日本古来の舞踊くらいしかすぐには思い浮かばない。草木でも今年実が多ければ翌年は少ない。いわゆる裏年というやつだ。プラスとマイナス、人間の栄枯盛衰の因果関係もそういうことだろう。親があまり偉くなるということは、花が咲き実がなり過ぎるということで、子供の代にはどうしてもマイナスになる。花でも実でも枝葉でも、剪定して間引く。間引かすに果物に執着して、すずなりにならせたり、満開に咲かせたりすると、木を弱らせてしまう。だから人間も、自分の力量よりいくらか控え目にするのが良い。あの人はもっと偉くなる人だ、あれではどうも気の毒だというところで止まるのが丁度良いのである。
そうすれば子孫にいくらか余力を遺すことになる。あんな奴があんなに偉くなって、と言われるような柄にない立身出世をすると、子孫が良くない。親は自分はもっと出世できたが、子孫のためを思いここで止まった。だから子供たちも偉くなるにしてもそこそこでいいと教えておく。要は身の丈より少し低いポジションの方がいい。欲を出して下手に身の丈以上の位置になると必ずといっていいほどその反動がくるということだ。本人は、儂は偉いとか、こういうことをやったとか、何とかかんとかいい気になっているが、お前本当にそうかと尋ねられて、俺は偉いから当然だと答えられるのは余程の馬鹿か狂人だ。良心の一片でもあれば、なかなかそういうことは言えない。
そう思っていれば、人が出世したからといって羨むこともないし、自分が窓際だからといって悔やむこともない。私欲の小さな自我に囚われて、日々の生活に追われているとなかなか全体が見えないし、子孫に余力を遺すなんてことは思いもしない。今が良ければ、自分が楽しければ、が優先してしまうのが人情だ。だが、よくよく考えたらその人情でストレスを多く抱え、心と身体に支障をきたしている。悠々自適とは一歩引いて生きることで得られる生きた方なのだろう。
『 人間は自然の一部なんだけどなぁ VOL228』 4月のコラム上へ
人間は自然から生まれた。だから自然の一部。自然と対決したり離れたりしてはいけない。自然の大枠の中で創造的、活動的でなければならない。ところが自然を操作し意のままのしようとした頃から自然と対立し、人間同士も争うことになった。文明の発展は喜ばしいことだが、自然から離れ過ぎて危険を伴うようになった。物質的、機械的ともいえる。自然の法則に人間の法則を合致せしめることはできるのだろうか。
ここにひとつ面白い実験がある。アメリカのリヒターという教授とアシスタントスタッフの研究報告。実験室で飼育されている鼠と野生の鼠を比較した。実験室の鼠は自然の変化と闘う必要もなければ、食物を漁る苦労もいらない。他の動物との命がけの闘争に苦しめられることもないから、自活能力は減退し闘う能力がなくなる。多数の飼い鼠の中へ一、二匹の野生鼠を入れると、飼い鼠が多いのにも拘らず、野生鼠に追いまくられ抵抗する力もない。飼い鼠は毒物細菌への抵抗力まで失われ、何不自由のない生活にも拘らず生存競争に耐えることができなかったというもの。
あまりに人工に過ぎて自然から離れると生命力を弱める。食物は自然に近いもの、薬も薬草などの自然に近い薬を活用する。教育も概念や形式的な知識を詰め込むのではなく、生命力を活性化させる実用的な基本を身に付けさせる。本来の人間の生きる意味を自ら見出せる教育をしなければならない。地球上に存在するありとあらゆるものに何らかの意味がある。あるから存在する。文明の発展と共に生活が豊かになり自然と人間の乖離が広がった。地球もいつかは滅星になるが、そのずーと前に人類の滅亡がある。今現在この星に生存している人類のひとりとして何かを為すか残すか。又はそれほど深刻に大げさに考えずとも自分の人生を全うするかくらいは心の隅に置いておきたい。
手先の手段的なものや理論的なものではどうにもならない。人間は人間の性質を変える他ない。人間の性格を変えるとは神の領域だ。恐竜が絶滅した時のように、人間の力ではどうにもできない外的又は自然の何かの力が作用して、人間はその愚かさに気づき強引に性格を変えざるを得ない状況に陥って、はじめて、その性格を変えなければならないと気づくのか。その時は人類の絶滅に近い代償を払うことも覚悟しなければならない。自然は「だからあの時あんなに忠告したのに」と言うだろう。あの時とは今この時かもしれない。
『 否 VOL227』 3月のコラム上へ
1826年21歳・秋、ジョン・スチュアート・ミル(イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家)は一種の倦怠感と憂愁に憑りつかれていた。「人生において自分の目的が実現されたと仮定せよ。自分の期待している社会機構並びに与論上のあらゆる改善が、完全に実現されたものと仮定せよ。果たしてそうなれば自分にとって大いなる喜びであり幸福であるか」すると抑えきれない自意識が明瞭な声で答えた。否。
いつの時代も改造、改革、変化、革命に狂奔している人々が存在する。大演説をやり、大論文を書いて盛んに社会の改造や変革を訴える。大衆もそういう声に耳目する。しかし果たして人間がそれによって救われるかというと答えは否。そういうもので救われるなどと考えるのは極めて浅はかで未熟な人間である。テレビ、新聞、SNS。色々なメディアを通し多くの人が主義主張、理論を語っている。ところが、本人に会ってみると大抵失望する。何故か?その人のいうところの思想、言論がその人の人格と一致していないから。その人のどこを押したら、ああいう音が出るのかと、お話にならないほど矛盾が多い。
なかなか人間というものは複雑で簡単に律することができない。虚飾、粉飾、偽装が多い。言動不一致は、例えば某政治集団が会議の時は国民の為というが、自分達だけの雑談になるとみんな虫のいい利己主義になってしまう。家に帰ると封建的暴君に変じる。人間というものは自分の都合がいいように思考が動く。然らば人間はミルのいう否を是といえる社会をつくれるのか。つくろうという意志があるのか。つくれるならそれはどういう方法があるか。人類はこの根本的な人類の問題を横に置いて、いくら文明を発展成長させたとしても、いつも自我の欲望を満たすため四苦八苦している。
人間の人間たる本質は純粋な徳性。愛するとか、報いるとか、手を差し伸べるとか、勤勉とか、、、。その徳性があって知能も技能も活きる。この徳性が不純なものならば、折角の技術や知識は危険なものになる。原子力を開発した科学技術は素晴らしい。だがこれを間違った精神で用いたならば殺戮兵器になる。人の心掛けにより正反対になる。そう人間にとって大事なものはその心掛け。幼少時の環境により大きく異なるのだろうが、どこでこの世に生を受けようが、長じるに従ってどのような教育を受けるかによって良くも悪くも人は大きく変貌する。何によって誰によって変貌できるか、若しくはできないのか。自身では選べない力が働くのだろう。ミルのいう否を是に人類はできるのだろうか。
『 滅亡まで90秒 VOL226』 2月のコラム上へ
中国の古典「大学」にある文言。緡蛮たる黄鳥丘隅に止まる。子曰く、止まるに於いて、その止まる所を知る。人を以て鳥に如かざる可けんや。(めんばんたるおうちょうきゅうぐうにとまる。しいわく、とまるにおいて、そのとまるところをしる。ひとをもってとりにしかざるべけんや)
緡蛮たる黄鳥とは、日本ではウグイスを黄鳥というが、ここでは春の鳥というくらいの意味。その鳥が小高い丘の辺りで春を告げる鳴き声がする。のどかで平和だなぁ。鳥でもどこで安んずべきか知っている。いわんや理性・知性のある人間はどこに落ち着くべきか、到達すべきかを最もよく知らなければならないのではないか。何が人類の安寧であり、幸福であるかということを知って、これを実現出来ないというのは、人にして鳥以下ではないか。鳥でも平和を愛しているのに、人間はいつも闘争ばかりやっている。というような意味。
人間の闘争本能は尽きることはない。いくらITだAIだといっても人間の本質は大昔から変わらない。否、変われないのが人間なのだろう。だからいつまで経っても争い、相手を排除しようとする。こういう人物が国や世界を動かす力を持つと世界中が混乱し、隅々の一般人にまで即時影響を及ぼす。今の世界は正にその真っ只中。一部の破壊者がルールを破り、我が意を通そうとする。随分と勝手なと思うが、所詮人の心の中はそういうもの。他人のことはいえるが、我身を振り返れば五十歩百歩ということだったりして。
コントロールできる心と出来ない心との葛藤。その解決方法は古い書物にはすべて書いてある。書いてあるが不思議なことに人類は何度も繰り返す。いくら文明が進んでも同じ過ちを繰り返すようにと天の計らいがあるのかとも勘ぐりたくなる。どこからきてどこにいくのか。永遠の真理を求め彷徨う人類。いつかはすべて消え失せてしまう儚さを知りつつ、今日という今を〇とするか×とするか。嫌なことや気に入らない出来事でも〇として捉えるかどうかでその後の運勢は変わる。せめてそう思いたい。
1月24日付けの新聞。米誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」は核戦争や気候変動などの脅威を分析し、人類滅亡を午前0時に見立てた「終末時計」の残り時間をこれまで最短の「90秒」と発表した。(2020年~2022年までは100秒だった)人間は黄鳥のようには生きていけないものらしい。
『 頼られる年齢 VOL225』 1月のコラム上へ
2023年令和5年が明けた。昨年はコロナの感染が見えない状況だったが、今年は収束の兆しが見え、マスクは外せないもののコロナ前の年始になったようで人通りも多いようだ。世界に目を転じるとロシアのウクライナ侵攻の先が見えず混沌とし、中国の台湾有事が現実味を帯びてきて、他人事ではなく覚悟が必要な年になるかもしれない。事件や事故や災害等の大きな転機がなければ日々の暮らしの変化はほとんどないと思って過ごしているが1年を振り返ってみると良いも悪いも1年前と違う自分がいる。それが5年前や10年前だとその差が大きい。
年齢とともに考え方やものの見方が真逆になることもしばしば。体力と記憶力の衰えを経験値でカバーできる上限も感じる。大きくそして小さく変わる社会情勢や身近な変化。人と人とのつながりで人脈は広がりをみせるものの何となく物足りない。老若男女や環境により感じ方が違うのだろうが、何だか軽い。人によっては大笑いできることが?ってこともある。反対に自分がこれはいいと思っても相手は?てなことも。多種多様でそれぞれがそれぞれでいいということだとは認めてはいるのだが、今の世の中何かが変。
物価の上昇が顕著で、生活が苦しい。国も給料を上げようとあの手この手を弄しているものの、企業側からしてみると働き方改革とやらで労働時間を制限して給料を上げろと言われてもなぁ、である。人の動きがコロナ前に戻る見通してがつきそうな今年は去年よりもマシだろう。物価が上がり、給料も上がり、金利も上がる。生活困窮者に公的資金がつぎ込まれているものの乗り越えられるのは一時。自ら脱して自活できるような支援が必要だ。
弱者への支援は必要だが、戦後の人々は廃墟の中から自力で切り開いてきた。その逞しさが現代人に感じられないのが何か変の答え。便利になればなるほど人間はものを考えないようになっていく。ほんの一部の人間が考え、与える側で考えない人間が与えられる側。与える側は富、与えられる側は貧。戦後の貧しい中から這い上がってきた年輩者には今の若者はどう映っているのだろう。確かに今後の日本を背負って行って欲しい若者は何人かいる。自分達が生きてきた証のエキスを注入したい若者はいる。そういう若者に自分にできることをやる。腹立たしいことも多いが微力でも何かの役に立つこと、誰かの役に立つこと、頼られれば応じることができる年にしたい。そういう年齢にもなった。