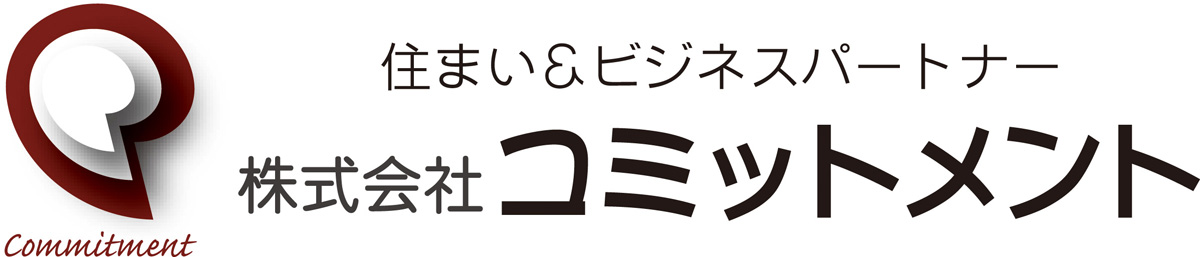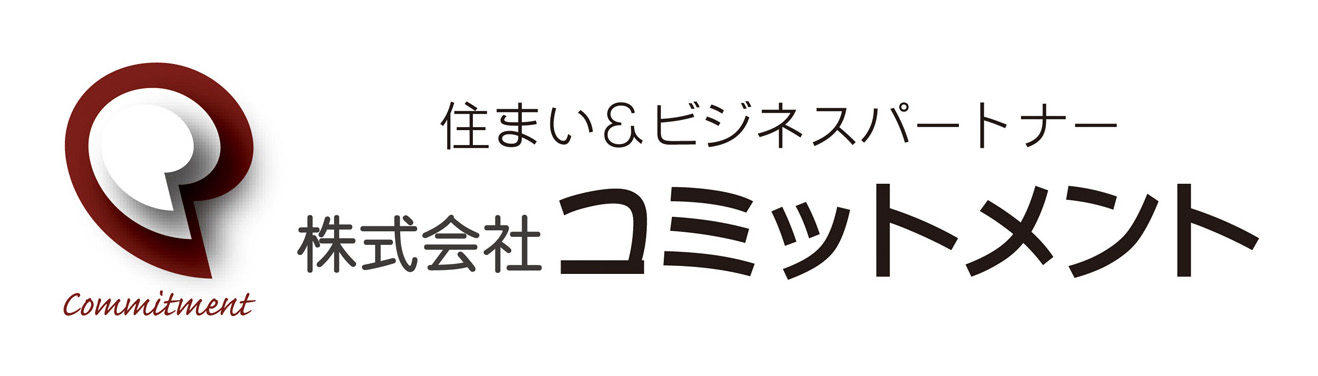【2025年コラム】
1月のコラム 2月のコラム 3月のコラム 4月のコラム
5月のコラム 6月のコラム 7月のコラム 8月のコラム
9月のコラム 10月のコラム 11月のコラム 12月のコラム
『 心を調える VOL260』 12月のコラム上へ
お釈迦様が修行を始めたばかりの弟子達を連れて旅をしていた。出家したばかりの弟子達は家族や故郷のことが恋しくなってくる。その途中で雨が降り出し、皆だんだん気が滅入ってきた。そこでお釈迦様は雨宿りをしようと、ある家に立ち寄った。ところが、その家は雨漏りのする家だった。仕方ないのでその家を出て、別の家を見つけた。その家は雨漏りはせず、皆も安心して休むことができた。そこでお釈迦様は説かれた。「こころ込めて葺かれたる屋根に雨降るとも、漏れ破ることなし。かくのごとくよく調えし心は、貪欲も破るすべなし」。
修行は降る雨を止ますことではなく、どんな雨でもそれに動じることのない生き方を目指すものだ。世間には冷たい雨も暖かい雨もある。困難な時だけでなく調子のいい状況にあっても、それに動じることのない心を調えて正しい判断ができるように修養する。自己を拠り所とし、自己の外に求めることはしない。よい習慣を身につけ自己中心の思いに囚われることなく、欲望を制御し、精神を調える。
いつの時代も行き先は見えない。その時々によってハードルは姿形を変え、目前に現れる。個人であれ、組織であれ、国であれ、この星であれ。先を見据え、今何をすべきか考える。そして今やるべきことを明確にして、打ち込む。ウダウダ思い悩んで堂々巡りしても、自分のできることと、できないことがある。それをはっきりさせ、天に任せることは任せ、できることは全力で行う。自分の生きざまは自分で見つけ切り開いていくしかない。そこに人生の醍醐味がある。それを味わう。お釈迦様は「一処に制すれば、事として弁ぜずということ無し」(一つの処に集中すれば、どのような事も見極められないものはない)とも言っている。
早12月。今年も色々な雨に濡れた。傘を差してくれた人もいた。振り返って自分は雨に濡れている人に傘を差してあげただろうか?心が乱れることはあっても、調わったことはあっただろうか?そうこうしているうちに、あれもこれもどんどん記憶の彼方に消えていく。この世の不思議と自分の立ち位置がつかめないまま、心が調わぬまま、除夜の鐘を聞くことになりそうだ。年の瀬に人生のファイナルを見据えると、何らかの足跡を残したいとの思いが湧いてくる。これでは心を調えるどころではない。いくつになっても、あぁ、煩悩は消えないなぁ。皆さま、今年もお世話になりました。よいお年をお迎えください。
『 睡起偶成(すいきぐうせい) VOL259』 11月のコラム上へ
睡起偶成:王陽明(おうようめい1472-1528)48歳の時の作と言われている。
四十余年 睡夢の中(うち) 而今醒眼(じこんせいがん) 始めて朦朧 知らず 日 すでに停午(ていご)を過ぐるを 起(た)って 高楼(こうろう)に向かい 暁鐘(ぎょうしょう)を撞(つ)く 尚 多く昏睡 正に矒々(ぼうぼう)たり 縦令(たとえ)日暮るるも 醒(さ)むるをなお得ん 信ぜず 人間の耳 尽(ことごと)く 聾(ろう)すと
いつの間にか四十余年を過ぎ、夢うつつの間に歳をとってしまい、今頃になって、やっと眼が醒めた。始めて朦朧として、やっとぼんやりと道がわかりかけてきた。気が付けば、もう昼下がり。起きて高楼に向かい、暁鐘を撞く。ふと気が付くと、多くの人はまだ寝込んでいる。たとえ日が暮れてもいつか目を覚ましてくれるだろう。人間の耳はみな聞こえない。だからとにかく何でもいいから暁鐘を撞くんだ。
世の中の仕組みや喜怒哀楽や悲喜こもごもや他人の気持ちが分かりかけてくる年齢が40代と言われるが、王陽明ですらこういうのだから恐れ入る。幼少の頃は何も考えず、毎日が来るのが当たり前。衣食住が当たり前に用意され、自分の思いが叶わないと駄々をこねる。それが白秋に向かう年齢になると感慨深くなる。当たり前の毎日が当たり前ではないことに気づく。さらに玄冬に近づくと、朝目覚めることが奇跡みたいに感じる。生命は永遠の相続。そのように感じる。生まれてこの方明日が来ない日なんてなかった。明日が来ると信じているけれど、明日は誰にも来るわけじゃないと実感する。
身体に伴う意識、打算、欲望、感情などは、生じたかと思うと消え、消えたかと思うと生ずる。煙の去来のようなもの。意識の深層が過去に連なり、未来に通じる。先祖代々、連綿と繋がる不思議な倉庫、宝蔵は無尽蔵で、子孫が何度か陥る窮地に、神秘な解答や指令をひょいと与えてくれる。だから、今ここに命を頂いた者は、きちんと年齢相応に世の中に恩送りをしていく使命がある。鐘を撞く使命がある、、、。 あ、その前にきちんと目を覚まさなくちゃ。
10月のコラム
『 メラビアンの法則 VOL258』 10月のコラム上へ
メラビアンの法則:1971年にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した、人と人とのコミュニケーションにおける情報の割合を示す法則をいう。それによると視覚情報(顔の表情や手などのジェスチャー)が55%、視覚情報(声のトーンや話し方)が38%、言語情報(話の内容)が7%という。
よくあなたは人の話を聞いていないと相手に詰め寄ることがあるが、この法則の通りだとすると言語情報が7%というから納得といえるのかも。話の内容に合わせ声のトーンや表情を変化させ、身振り手振りを加えることにより、説得力が増し、相手がこちらの言わんとしていることを理解してくれるようになる。自分の伝えたいことが正確に意図した形で伝わるには、視覚、聴覚、言語のすべてに矛盾がないようにすることが重要ということだ。ところが、これが意外と難しい。どうしても言語で相手に伝えようとするあまり、表情や声のトーンを疎かにして、話の中身が?になることも多い。分かり易い例は、あの時あの人との会話は楽しかったというものの、肝心の話の中身が何だったんだっけ?という場合がある。あの人のにこやかな笑顔や笑い声は思い出せるが何の話が思い出せないケースは、正に視覚情報55%、聴覚情報が38%で計93%の世界だ。
メラビアンの法則は話の内容と非言語情報が矛盾する状況で、相手がどちらの情報に影響を受けるか検証した研究に基づいている。話の内容そのものよりも声のトーン、高さ、抑揚、話し方、そして、表情、ジェスチャー、身振り手振り、服装、態度なでど相手が言葉を受け入れるキャパが広がったり、狭くなったりするということだ。付き合いが長くその人の性格が分かっている場合は、話の内容以前に最初から話半分で聞こうとか、この人の話はきちんと聞いておこうとか相手によってこっちが勝手に心構えをしていることもある。自分では100%相手に分かるように話しているつもりでも、それは自分の「つもり」なのだ。自分はAを欲しいと相手に言っても、相手の返事は「Bもありますよ」と言う。こっちが欲しいのはAなのに「Bもあります」では答えになっているようでなっていない。そういう時は「BもありますがAがいいんですね」とかの返答なら会話として成り立つ。相手の言葉を一度受け止めてから自分の思っていることを伝えることはコミュニケーションをとる上で大事な能力だ。
自分の話したいことだけ話していては、いずれ聞いてくれる人が少なくなっていく。喋る分の2倍聞くことを心掛ければ、会話もはずみ又会おうということになる。口はひとつ、耳はふたつ、なのだから。
『 老人脳 VOL257』 9月のコラム上へ
いくつになっても脳が若い人と老化が進む人の差はどこにあるのか。「スーパーのレジ待ちの列に割り込む老人」「人目をはばからず、店員に怒鳴り散らす老人」そんな迷惑老人が多くなった昨今。なぜ、彼らは自省できないのか。それは脳の老化、老人脳であることが原因だ。脳の老化は30代から始まるが加齢=老化ではない。70代でもアクティブに幸せなシニアライフを送っている人たちもいる。そんなスーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方を紐解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るきっかけにしてもらう。西剛志(にし・たけゆき)著。「80歳でも脳が老化しない人がやっていること」という本を読んでみた。
脳はつながりを感じるとき、最高の状態になる。回復力もたかまり、エネルギー溢れる状態にしてくれる。つながりとは人でなくても、自然や動物や楽しかった思い出や、要はワクワク感とかドーパミンとかオキシトシンとかのいわゆる幸せホルモンが出るような生活をしていると老人脳にはなりにくいという。いい意味で自分のやりたいことをやる、自由に生きる、無理をしない、いろんなことに挑戦してみる好奇心を持つ。なぁんてことを「角度」を変えて論じている。
まぁ誰しも歳はとるものだが、別に老人だからキレるということでなく、若者でも老人脳の人が増えているともいう。キレやすい人が老人脳という訳だ。そして言葉、やはり言葉は大事だ。脳にマイナスになる「使わないほうがいい言葉」として、疲れた・嫌だ・運が悪い・できない・難しい・無理・時間がない・体力がない・気力がない・面倒くさいetc.言葉は脳に影響を及ぼすことを「脳のプライミング効果」という。ニューヨーク大学の実験で学生に「孤独」「忘れやすい」「退職」など年配者のような言葉を使ってもらったところ、歩くスピードが遅くなったという。脳が体をコントロールしているということだ。「疲れた」と言ったら、疲れていなくても脳が体に疲れたと信号を出してしまう。「わからない」「難しい」などの言葉も危険な言葉だ。
そうはいっても日常会話でマイナス言葉を全く使わないという訳にもいかないだろう。そこでマイナス言葉を相殺してくれる言葉が「ありがとう」。「ありがとう」をなるべく多く話すことを意識しましょうということだ。例えばエスカレーターでドアを開けて待っていてくれて人に「すみません」というより「ありがとうございます」と言った方が運はよくなる。ということで加齢でも老化しないよう〇〇をやろうと思う。さて〇〇になにを入れるか考えねば。
『 義に生きる VOL256』 8月のコラム上へ
今年5月、航空自衛隊の練習機が愛知県犬山市の入鹿池(いるかいけ)に墜落した事故を覚えているだろうか。もう3ヶ月も前になるので覚えていないかもしれないが、思い出して欲しい。搭乗の二人の自衛官は操縦桿を握ったまま殉職した。ニュースでは殉職した自衛官の捜索を報じていたが、それ以上の報道はなかったようだ。それ以上とは何か。民家を避けるべく機体の捨て場所を探す決死の勇姿のことだ。小牧基地を離陸して機影がレーダーから消えるまでわずか2分。手練れのパイロットに操縦のミスはまずない。周辺には住宅や小学校、明治村などが点在しており、13キロ先の池までなんとか飛行したものの、すでに時遅く脱出はかなわず、二人は練習機と運命をともにする。自分達が助かることを優先して、機体から脱出すれば機体は制御を失い、地上に墜落することは明らか。そうなればどれだけの死傷者が出るか。二人は自分達の命よりもより多くの命を守った。メディアの一部でもいいからこの二人の自衛官としての矜持を報道して欲しかった。
もう一つ。1999(平成11)年、埼玉県狭山市の入間川(いるまがわ)河川敷墜落事故。この時も操縦士は脱出の機会がありながら、最期まで操縦桿を握っていた。報道機関は、墜落時に送電線が切断されて多くの民家が停電して、大混乱に陥ったと騒ぎ立てるばかりで、殉職した隊員や遺族に弔意はほとんどなかった。これに対して、一人の女子高生が新聞に投稿した。「どの報道も、高圧線が切断されて停電が起こった、ということが中心で、最期まで自分の命の危険を顧みず、民家に墜落しないように、と必死に操縦された隊員を称える言葉はありません。どうしてですか?操縦士の方々が命を投げ出されたおかげで救われた命があったかもしれないということを分かってもらいたいのです」
残念だが、事故は起こる。まるっきり予期しない、予期できない、まさかこんなことがこんなところで、ということが往々にしてある。その時にどう対処するか。見た目とか、地位とか、名誉とか、お金持ちとかは関係ない。いざという時に公を優先して、命を投げ出せるか。自分を犠牲にして、多くの人を救えるか。義に生きる覚悟は常に秘めておかねばなるまい。
論語:歳寒くして、しかる後に松柏の彫(しぼ)むに後(おく)るるを知る(寒い季節になってはじめて松や柏などの常緑樹が、他の草木が枯れるのに、枯れずに残ることが分かる→普段は目立たない人でも、困難な状況に直面した時にその人の真価や人間性が明らかになる。
『 水雲問答 VOL255』 7月のコラム上へ
雲:国を治めるには、人心を悦服(えっぷく)させることが肝要かと存じます。人々が悦服しないと、どんなに良い法律をつくっても、立派な政治は行われません。為政者に、施し(人々を納得させ満足させること)、寛(寛大な気持ち)がなければ、人心は悦服しないでしょう。人民を心服させるにはどうすればよいか、俗にいう頭が良いリーダーに部下の心は服さないというのはどういうことか、ご意見を賜りたいと存じます。
水:施しに過ぎると、むやみに賞を濫発するという弊害があり、寛に過ぎると、規律が緩んでだらしなくなるという弊害があります。このように人民や部下に褒美を与えてご機嫌をとったり、失敗を大目にみて人心を得ようというのは、枝葉末節です。自らの徳と日頃の行いが、いつとはなしに人々を感化していくとことであれば、人々は心服するものです。下の者がリーダーに心服しないのは、権略つまり下心があるのではないかと警戒して信用しないからです。施しもまた程度と方法によっては結構ですが、それによって人心を得ることはできません。寛も必要ですが、度が過ぎて、重箱の隅をほじくるように細かいところまで立ち入ると下の者は堪えられないものです
自由気儘に任しておけば、いい人だ、やかましく言わない、勝手にさせてくれるということで評判がいい。しかしそれは「未熟なる者」がすることである。自分に備わっている徳が自然に相手を化していく。とかくリーダーは頭がいいものだから、色々手段、方法、権略というものに偏る。行き着くところ、あの人がいうのだから言うことを聞こう、と人心が服するような人になれということに尽きる。上に立つ者はこまごまと立ち入らず、よく人を識り、任せるところは任せる。肝の据わったリーダーがいる組織は、風通しがいい。
3年に一度の任期満了に伴う参議院選挙は7月3日公示7月20日投票が決まった。自民党は一人当たり2万円、子どもや住民税非課税世帯には追加で2万円を支給することを公約にして、野党はそれぞれ消費税減税やゼロにすることを公約にして支持を広げようと躍起になっている。小泉農水相の備蓄米の放出で米の価格が下がり、内閣支持率が持ち直したが、国民はそんなに単純ではない。目の前の甘い誘いに乗って投票するとは限らない。
荀子(じゅんし)に「治人有れど 治法無し」の名言がある。国が治まるのはこの人がいるからであって、この法律があるから国が治まるということではない。現状の政治家の顔ぶれをみると「治法あって、治人なし」の感があるが、、、果たして選挙の結果は?
『 自分は何者? VOL254』 6月のコラム上へ
何気なく使っている一人称の「自分」とはいい言葉である。私、俺、僕、小生、拙者、己等一人称の言い方は色々あるが、その中で「自分」とは大袈裟にいえば、日本人独特の相手を思いやる思慮深い意味が込められているのではないか。つまり、自と分とを合わせ「自分」という円満無碍(えんまんむげ)、全てのものが調和して、妨げがない世界を指しているのではないかと。そういういい言葉だが、人は自分、自分と言いながら、自己、「私」をほしいままにしている。「私」の成り立ちは諸説あるが、禾(のぎへん)、米を一人で抱えるムからきているというのがスッキリするようだ。因みにムをオープンにしたのが公。
自分自身を知ることは難しい。時々「自分は一体何者なんだ」のような感覚になる。自分がどういう素質や能力を与えられているか。まずはそれを知るのが「命を知る」知命。知命に気づき発揮して、自分を尽くすのが立命。だが、実は自分自身って結構取り扱いにくい。そこで占いや予言や縁起などというものに翻弄されたり、頼ったりする。命を立てるとはいかなくても、せめて命を知らねばなるまい。先天的に賦与されている能力は誰にでもあるが、目に見えるものではない。それは後天的修養によって成就する。修養次第、徳の修め方でどうにでもなる。決して浅はかな宿命観などに支配されて、自分で自分を見限るべきものではない。
よくスポーツなどでゾーンに入るとか無心になれたとかいうが、人間無心にはなかなかなれない。色々の事物に心を捉えられ、知らず知らずにそのものに自分を支配される。即ち、自分が何者かが見えなくなる。自分が自分を使いこなせない。多くの人は生まれたままの運命を受け入れるが、世に名を成す人は自分で自由に変化造成し、運命をコントロールする。「命は我より作(な)す」なのだ。
仁義道徳のような精神的なものは、誰でも心の中に備わっている。努めることにより、人間性として醸成する。仁義道徳と同じく功名富貴も心中にあるが、これは我が身の外にあるものだから、天運が味方しなければ得られるものではない。人を欺いたり、様々な謀計を巡らせて求めようとしても天の理がなければ成るものではない。人はよく「自分の思い通りにはいかないものだ」と嘆くが、その思い通りにいかないことが本当のことだったり、真実なのかもしれない。思い通りにいかないということは自分の身勝手さを戒める天の計らいか。人の一生は自分探しの旅のようなもの。一体自分って何者?
『 人類の安寧 VOL253』 5月のコラム上へ
20世紀の文明と文化は西欧的な合理的の精神が築いたものといえる。その個人的な物の見方、感じ方、考え方、要するに物事を分析、解明し、論理的に組み立てていく思考方法が、エネルギーになっていた。結果、現代の物質的に豊かな社会をもたらし、同時に、多岐多彩にわたる国際社会の諸現象を派生した。それが、次第に異文化の尊重、相互に融和し合う精神を失い、自己本位の争い事が絶えない世界へとなった。
20世紀に限らず、いつの世にも争い事は絶えないのだが、21世紀になって4分の1が過ぎた今もその状況は変わらない。一体人類は何を学んできたのか。もの凄い勢いで目に見える物質的進歩はしている。物質的進歩と同じくらい精神面が進歩しているのか。益々、自分主義の独善的、排他的な傾向が顕著になっていくようだ。今だけ、自分だけ、金だけ。自分を中心に世の中回っているならそれでもよかろう。それぞれの自分ファーストが争い事を助長して、終わりのない争いを続けている。力のあるものが力任せに圧力をかけ、力のないものが淘汰される。残った者同士が更に力で相手を屈服させるべく、力をつけようと躍起になる。力と力のぶつかり合い、どちらかが白旗を上げるまで争いを続ける。結果、最後に得るものは一体なんなのだろう。勝者はいるのだろうか。易姓革命の歴史を繰り返してきた現在の中国、ローマ大帝国の歴史が教えているではないか。
人類の争いを止めることはできないようだ。常にどこかの地域で争い、殺戮が行われている。物質的に豊かになればなるほど反比例して精神は置きざれにされ、その差は開く。そして貧富の差となり、富のある者、権力のある者が牛耳ろうとする世界が続く。いい加減、目覚めてもいいと思うのだが、人間の欲望をいうものは留まるところを知らない。おそらくこれまでのように、これからもこの星に安寧が訪れることはないだろう。そう、歴史が物語っている。自分ひとりで世の中を変えるなんてことはできないかもしれないが、誰かに優しい人間でありたい。
郡山のリーダーが新たになる。初心を忘れず、市民に優しい市政を望む。但し、郡山だけ良いということはない。郡山ファーストでなくても大局を鑑みてしっかりとかじ取りをして欲しいと願う。我々市民も後押しができるよう心掛けておかなければなるまい。足元の思いやりの一歩が最終ゴールの人類の安寧に結びつく。
『 悪口 VOL252』 4月のコラム上へ
人は悪口やネガティブな言葉が多いと心身にどのような影響を受けるのか。精神科医の樺沢紫苑(かばさわしおん)氏は悪口の心身への影響について、想像以上に脳と身体に悪影響を及ぼす、脳と身体へのストレスが増えて、不安や恐怖を感じやすく、認知症のリスクが高まり寿命も縮まるという。また東フィランド大学の研究によると、世間や他人に対する皮肉、批判度の高い人は認知症のリスクが3倍という。悪口を言い続けていると、ストレスホルモンであるコルチゾールを分泌する。コルチゾールは、記憶の保存に関わる海馬の神経を破壊し、前頭前野の神経ネットワークのつながりを40%も破壊する。悪口を言うことで、認知症を発症するほどのダメージを脳に与えるということだ。
「ポジティブ思考」と「ネガティブ思考」の人を比べた研究では、「ポジ」の人は「ネガ」の人より10歳以上長生きし、心疾患の発症率が半分以下との検証結果がある。つまり皮肉・批判的な人は死亡率が高いということ。悪口を言うとアドレナリンが出る。一日の中で何度もアドレナリンを出す生活は心臓に悪い。
よく居酒屋等の飲み屋で上司や会社の悪口大会が開かれていたり、ママ友仲間で、姑や夫の悪口を言い合っていたりする。悪口を言う人は「悪口を言うとスッキリする。悪口はストレス発散になる」と言うが、これは間違い。競技や喧嘩をしている人はアドレナリンが出る。戦闘状態になるとアドレナリンが大量に分泌される。悪口は言葉による攻撃。悪口を言っている時、脳は戦闘状態となり、アドレナリンを分泌する。アドレナリンによる高揚感は「楽しい」と認識され、脳の過剰な興奮を「ストレス解消」と誤認する。
誰でも悪口を言われると、とても嫌な気持ちになるだろう。悪口を言うというのは、言われると同じくらい脳に反応が現れる。侮辱の言葉、ネガティブな言葉を発すること自体、脳には害だ。他人の悪口を言っているつもりが、自分が悪口を言われているのと同じ悪影響を自身に受けている。
樺沢紫苑氏は感謝の効果を十分に出すには「悪口」1回に対して、「ありがとう」を5回程言う必要があるという。悪口・誹謗中傷、あるいは「自分はダメ、無理、出来ない」といったネガティブな言葉は極力意識して言うべきではないし、自分自身にも周りの人たちにも影響は大きい。つい言いたくなる言葉を一呼吸置いて、悪口屋にならないよう自制が必要だ。言葉は言霊。良いも悪いも言葉の影響は大きい。
『 皇統 VOL251』 3月のコラム上へ
2020年3月。国連の女性差別撤廃委員会から日本政府に送られてきた質問状の中に「皇室典範について、皇位継承から女性を除外するという決まりがあるが、女性の皇位継承が可能になることを想定した措置について詳細を説明せよ」という文言があった。つまり国連は、皇位継承が男系男子に限られているのは女性差別であるという。日本の歴代天皇は、現在の今上(きんじょう)陛下にいたる126代すべて、父親を辿れば初代神武天皇に繋がる血統、即ち男系で受け継がれてきた。長い歴史の中で、皇統断絶の危機は幾度もあった。その度に知恵を絞り、一時は女性天皇を擁して懸命に皇統を守り抜いてきた。女性天皇を擁しても女系天皇にはしなかった。
「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の欠けたることも 無しと思へば」と詠んだ藤原道長や織田信長そして豊臣秀吉も徳川家康も天皇の地位を奪い、その地位に就こうとはしなかった。天皇はそれほど畏怖すべき存在ということだ。これまで一般女性が結婚を通じて皇族になったケースは多くあるが、一般男子が皇族になることは許されておらず、男系男子による皇位継承は女性差別とは別のものである。そもそも2685年(AD2025+BC660)の長きにわたり守り抜かれてきた我国の根幹を外からの干渉により変えてよいものなのか。神武天皇以来連綿と受け継がれてきた万世一系の歴史が万一途絶えてしまえば、日本の中心が失われてしまいかねない。
2024年10月29日、国連の女性差別撤廃委員会は最終見解で、皇位を男系男子に限る皇室典範は女子差別撤廃と相容れないとして、改正を勧告してきた。勧告というと強大な権威から命令されたという印象を抱くが、お勧めするという程度の意味合いで強制力はなく、どう受け止めるか当事国が決めるということのようだ。もうひとつ、何故国連がこの問題を取り上げたのか。女系天皇を容認したい邦人が平素から熱心にロビー活動を行い、国連のテーブルに乗せた。つまり日本人自身がこの問題を招いたということだ。
天皇のことをほとんど取り上げない戦後教育の中で育った多くが、皇室は税金で贅沢な暮らしをしている。天皇は不要だとの声も聞かれる。天皇は国の平和と国民の安寧を祈る人。年間を通じて膨大な公務を全うし、祭主として重責を一身に担っている。皇室の126代、2685年に及ぶ歴史は世界でも群を抜いて、各国の羨望の的となっている。断絶が一度もなく、万世一系で受け継がれてきた日本の皇室はまさに奇跡といえる。決して途絶えさせてはならない。
『 承認欲求 VOL250』 2月のコラム上へ
情報発信がSNS中心になったと言っても過言ではない昨今。他人から一目置かれたい、自分を認めて欲しい、という欲求を満たそうと、SNSを駆使し、閲覧者からのリアクションに期待する今時の風習。他人の評価が気になって仕事や普段の生活に支障をきたすまでにエスカレートしてしまうことも。こうなると発信する方もリアクションを返信する方も歯止めが効かなくなり、自分自身を見失う危険性を孕んでいる。人の気を引いて、チヤホヤされていたい。他人から賞賛されたい、他の人が仲良くしているのを見ると嫉妬心が湧く。本能のひとつともいえるのだが、コントロールしないと誰も相手にしてくれなくなる。
幼少時は我儘も容認されるが、長じるに従い、分別ができるようになり、我慢することも、相手を思いやることもできるようになる。ところが中には抑制が効かないまま大人になる人がいる。自分の思い通りにいかないと、暴力的になる人、殻に閉じ籠ってしまう人等。そういう人は素直に自分を受け入れることができず、自分の価値を認めることができず、自分の短所やコンプレックスを気にかけ、挙句に自己嫌悪になる。その穴埋めに自分はここに存在していると認めてもらいたいという欲求を満たすための手段としてSNSで発信する。対人関係を苦手としているので、見えない相手を対象として。
この承認欲求に男女の差があるという。個人差があり一概に言えないが、他人に認められたい、評価されたい、という欲求は男性が強く、嫌われたくない、変な人と思われたくない、という欲求は女性が高い。どちらかというと男性は女性よりも地位や名誉に固執傾向が強く、争い事に発展することもしばしばだが、女性は、まあまあ、この辺でいいでしょう的な中和を求める。それで世の中が成り立っているとも言える。
承認欲求が強い人ほどSNSを頻繫に利用し、スマホ依存に陥りやすくなるという。老若男女誰でも、いくつになっても、誰かに繋がっていたいし、認めて欲しいという思いは多かれ少なかれある。認めて欲しいなら、自分も相手を認めればいい。互いに承認し合えば意見の食い違いを擦り合わせできる。自分の感情も相手の感情も尊重できれば、ストレスも少なくなるのに、一筋縄ではいかないのがこの世か。歳を重ねると物欲は少なくなるが、自分の存在を認めて欲しいと欲求は、いくつになってもなくなることはない。誰かに支えられて、今ここに存在していることを忘れてはならない。
『 ポップコーン脳 VOL249』 1月のコラム上へ
2025年が明けた。令和も7年目になった。年賀状じまいが定着し、お正月の風物詩が少しずつ少なくなり、初売りも高揚感がイマイチ。娯楽やニュ-ス等の情報源はスマホでほぼ足りるから、テレビ離れに拍車がかかっている。況や新聞や本も。
ポップコーン脳:思考が次から次へと飛び移ってひとつのことに集中できない状態。多動性と新たな刺激を渇望する状態。注意力が散漫な状態を指す俗語。ポップコーンの粒が不規則に弾けるように、頭の中であれもこれもと考えや課題が次から次へと飛びかう現象。情報過多により、まとまりがつかず、どれも半端で終わってしまう。オンラインで入手できる膨大な量は、認知能力を圧倒し、情報の処理と保持に課題をもたらす。ペースの速いライフスタイルが、職業的、社会的プレッシャーとなって、複数の課題を同時に処理しなければならない現代。皮肉なことにこれが注意力の散漫の一因となっている。ポップコーン脳が個人と社会に及ぼす影響として、生産性の低下、不安やストレス等の精神衛生のリスク増加、学業成績の不振等が上げられる。絶え間ない心の飛び移りにより、生身の人間と繋がることができなくなると、社会的孤立、共感する力が低下する。
では、どうするか。心のメンテ、気持ちのリフレッシュ、精神の安定の時間をつくることだ。外からの騒音を遮断するデジタルデトックスやマインドフルネスといった瞑想の実践、集中力を高め、コントロールできる時間を意識してつくる。お薦めは睡眠の前。横になって眠りにつく前にはスマホ等は見ないで、目を閉じて今日一日の振り返り、今ここに集中する。この時に額の中央部、眉間(みけん)所謂第三の目に気持ちを集中させる。深呼吸して、集中して、気持ちを落ち着かせ、振り返り、なりたい自分をイメージする。そうすると眠りにも自然と入ることができる。気持ちをリフレッシュして、一日のいいことも嫌なこともリセットして、なりたい自分のイメージをする。強くイメージすれば夢は正夢になる。
毎年区切りの1月1日に今年の抱負を心に誓うものだが、負を抱く覚悟があれば叶うし、なければ叶わない。リスクを負わなければリターンは得られない。情報を得たとしてもそれを処理する能力がなければ通り過ぎる。自分にとって有効な情報かどうか判断して拾うか捨てるか。新年早々、情報過多で頭がパンクしないよう、頭デッカチにならないよう、ひとつひとつできるところから着実に確実に堅実に。