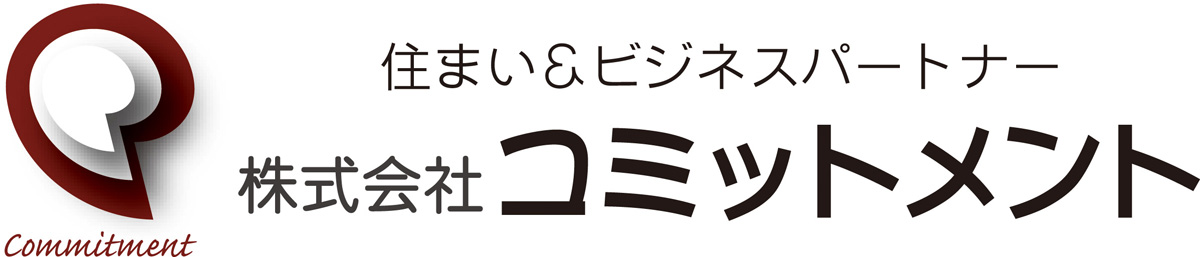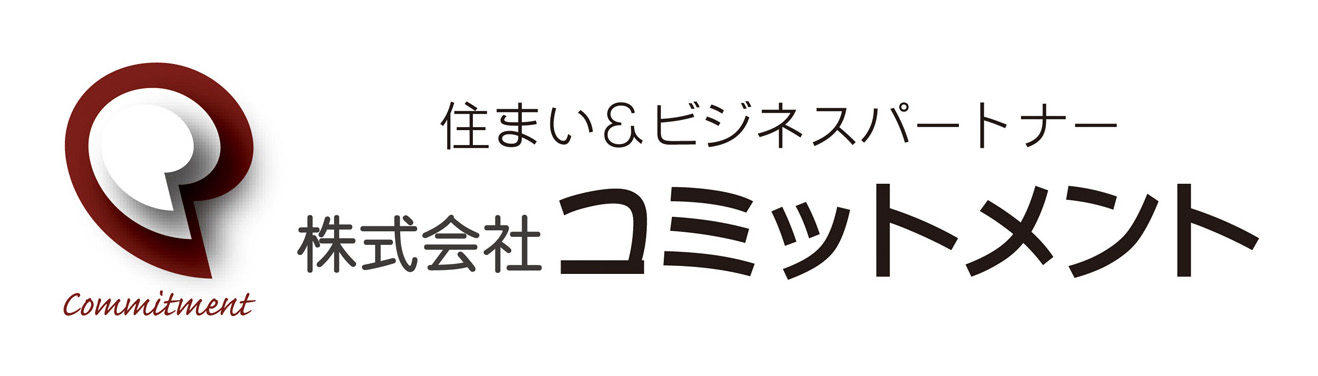Q&A
Q1 相続人に行方不明者がいる
父が亡くなりました。相続人は、私と弟3人の全部で4人です。遺産分割協議を行いたいのですが、一番下の弟とは3年前から音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、行方不明の弟を除いて3人で遺産分割協議を行うことはできますか?
A できません。
行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。

一口に音信不通といっても、
①連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、
②生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合、
③7年以上②の状態が続き生きているかどうかも分からない場合、があります。
①の段階では、まず行方不明者の住所を特定します。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、現在の住所を確認できます。現在の住所が特定できたら、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。このような方法でも、住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合には、②の段階に進みます。
②の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。

③の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となります。(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。
このほか船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(危難失踪)。
Q2 相続人に未成年者がいる
40歳の夫が交通事故で亡くなりました。相続人は妻である私と小学生の子供2人です。夫名義の自宅を私の名義に変更したいのですが、どのように手続きをすすめたらよいでしょうか?
A 未成年の相続人がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。そして、相談者と特別代理人との話し合いで、自宅を相談者が取得するという遺産分割協議をします。
法律では、20歳未満の未成年者は、賃貸借契約などの法律上の手続きをするためには、親権者である親の同意が必要です。それは法律上の物事を決定するための判断能力が不十分であり、法律上の手続きをする社会経験が不足している未成年者を守るためです。未成年者が遺産分割協議を行う場合にも、親権者である相談者の同意が必要となります。
ただし、今回のケースでは、未成年者だけでなく相談者も相続人なので注意が必要です。本来なら、未成年者の代わりに相談者が遺産分割協議に参加しアドバイスをできればよいのですが、相談者自身も相続人なので、自分一人で何でも都合のよいように決めてしまうことができます。こうした事態を防ぐために、親権者と未成年者との間で利害関係が衝突するようなケースでは、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
未成年者が2人いる場合には、特別代理人も2人選任する必要があります。選任後、相談者と未成年者の代わりの2人の特別代理人の間で遺産分割協議を行います。以降は通常の相続登記手続きと同じです。
Q3 相続人の一人が海外に住んでいる
父が亡くなりました。相続人の一人である弟がアメリカに住んでいます。父名義の土地と建物を私名義にしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
A 通常通り遺産分割協議を行い、日本の法務局へ相続登記を申請します。ただし、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにアメリカの日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。
日本国籍の方が亡くなった場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、相談者の相続人の一人である弟が海外に在住とのことですが、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありません。そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書に弟本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。
不動産を取得する人が海外在住の場合
土地や建物といった不動産を取得される方が海外在住の場合、上記のような理由から住民票の代わりに在留証明書を取得しなければなりません。この在留証明書も在外公館(日本領事館)で取得できます。以上のように、相続人の方のうち、一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。
Q4 借地権を相続した
借地上に建物を建てて住んでいた父が亡くなりました。父名義のこの建物を私が相続して今後も住み続けるには、地主の承諾が必要になるのでしょうか?なお、相続人は私と兄の2人だけです。
A 借地上の建物及び借地権を相続する場合、地主の承諾は必要ありません。相談者が相続するということなので建物を自分名義で登記し、地主に土地の借地権を相続し、今後の借地料を支払う旨の通知をすれば足ります。できれば借地契約書も自分名義で地主と書き換えておいた方がいいでしょう。
又、将来地主が代替わりしたら新たな土地の所有者(地主の相続人)と借地契約の書き換えておいた方がいいでしょう。契約の期間は父名義の契約を引継ぎます。 借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことです。

借地権も財産なので相続の対象になります。たとえ相談者がお父さんと同居していなかったとしても借地権を相続することができます。
「借地権者がなくなったのだから、土地を返してほしい」という地主の要求に応じる必要はありません。この点、借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。
借地契約書の名義を書き換えの際、書き換え料の請求をされることがあるようですが、支払う義務は全くありません。ただし、借地契約書の作成を専門家に依頼する場合は作成手数料がかかります。
尚、相続した借地権が定期借地権の場合も当然に相続することができますが、存続期間が定められていて、存続期間満了すると借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりません。定期借地権とは、存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていません。
Q5 相続登記はいつまでするのか
祖父が亡くなってから5年以上も祖父名義の家の名義変更をしていません。相続登記を今からしても大丈夫でしょうか?相続登記はいつまでに行わなければならないのでしょうか?
A 相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、遺産分割協議及び相続登記は早めに行うことをお勧めします。何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと以下のような問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきます。
①役所で被相続人の住民票や除籍謄本(改正原戸籍)等、相続登記に必要な書類が取れなくなる。 住民票は5年、戸籍は150年の保存期限があります。
②相続人のうちの誰かが亡くなり、権利関係が複雑になる。たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と長男・次男の三人、相続財産は自宅のみで、母親がその自宅を相続したい場合を考えます。すぐに遺産分割協議をして、母親名義に相続登記をすれば問題ありません。しかし、何年も遺産分割協議をしないで放っておいて、長男が結婚した後に亡くなってしまったとします。そうすると長男の子供も相続権をもつことになります。自宅を母親が相続できるよう遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お金を要求してくることも考えられます。

③相続人の高齢化により、遺産分割協議を行いにくくなります。相続人の一人が認知症等になり、判断能力が低下してしまうと、裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができなくなります。成年後見の申し立てには数か月~1年位の時間と費用数十万がかかります。
④相続人の一人の債権者が、法定相続による相続登記を代位登記で行ってしまい、その相続人の持分を差し押さえてしまう危険があります。この時点で遺産分割協議を行っても、債権者に対してお金を支払わなければ、他の相続人の名義に相続登記をすることが難しくなります。
以上のように、長期間相続登記を行わないでいると、さまざまな問題が発生して、いざ本当に相続登記を行いたいときに、余分な費用と時間がかかったり、相続登記ができなくなるという危険もあります。特に、不動産を売却したり、お金を借りるため不動産を担保に入れたりするような場合には、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに行っておくことをお勧めします。尚、相続税の申告は、相続開始後10か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
※代位登記:債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができる。(この事を債権者代位権という)つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できる。( この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)という)
Q6 遠方の不動産を相続登記したい
私は郡山市に住んでおりますが、父名義の仙台市の不動産の相続登記手続きは可能ですか?

A はい、可能です。オンライン申請を利用して、仙台市の法務局に相続登記を申請します。相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局へ行って、相続登記を申請しなければなりません。しかし、登記手続きもIT化がすすみ、現在はすべての法務局でインターネットを通じたオンライン登記申請が可能です。このオンライン申請は、設備や環境が整っていれば大変便利です。直接仙台市の法務局へ行かなくても、パソコン上で登記申請ができるからです。
Q7 遺産分割協議がまとまらない(争続)
父が死亡し、相続人である私と兄と妹の3人で何度も遺産分割協議をしたのですが、誰がどの財産を取得するかでもめて、なかなか協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか?父は遺言書を書いていませんでした。

A まずは、弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらいましょう。それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官(裁判官)によって遺産分割の審判(判決のようなもの)がなされます。
遺言書がない場合、法定相続分以外の割合で遺産を分割するには、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意しなければなりません。1人でも協議に反対の相続人がいるなら、遺産分割協議は成立しません。遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親族であってもなかなか話し合いがまとまらないケースがあります。特に当事者である相続人だけの話し合いでは、収集がつかなくなることもあるでしょう。弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもらうなら、中立の立場から法的な意見を聴くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。それでも協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用します。
遺産分割調停【必要書類】
- 申立書
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡した記載のあるものまですべて)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産のリスト
- 不動産の登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
- 固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)
申し立てが受理されると、裁判所から相続人全員に呼出状が送られてきます。調停手続きでは、2人の調停委員(弁護士や民生委員など)と1人の裁判官が立ち会い、対立している相続人を1人ずつ交互に調停室に呼び、それぞれの意見や希望を聞きます。調停委員は、それぞれから聞き取った希望や解決策を相手の相続人に伝え、それを何度も繰り返して、妥協点や解決策を探っていきます。相続人全員が納得し調停が成立すると、調停調書が作られます。調停調書は判決と同じ強い効力があるので、たとえ後で心変わりをした相続人が調停調書に反対しても、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。一方、遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、次の遺産分割審判手続きに移ります。
遺産分割審判手続
審判手続きでは、家事審判官(裁判官)がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等や遺産の種類等を考え、また、それぞれの相続人の意見を聞いたうえで、遺産分割の内容を決定します。審判の決定も判決と同じ強い効力があるので、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。尚、相続税がかかるケースでは、遺産分割協議が成立しないまま何年も経過してしまうと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例等、相続税の軽減を受けられなくなることがありますので注意が必要です。
Q8 借金を相続したくない
父が多額の借金を残して亡くなりました。親の借金は相続人である私が支払わなければならないのでしょうか?相続人は私と母だけです。尚、他の親族に父の兄であるおじが一人います。
A 相続が開始したことを知った時及びあなたご自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、借金は相続しなくてすみます。
A 【相続放棄の申述に必要な書類】
①申述書
②相続人の戸籍謄本
③被相続人の除籍(戸籍)謄本
④被相続人の除住民票
相続放棄の申述が認められると、借金はすべて相続しないですみます。ただし、相続放棄をすると、不動産や預金などの相続財産すべてが相続することができなくなります。財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。相続放棄をする前に、相続財産をよく調査して財産よりも借金のほうが多いか調べておきましょう。尚、母親とあなたが相続放棄の申述をして認められると、相続権はおじに移ります。第一順位の相続人(子供)が相続放棄すると第二順位の相続人(親)へ相続権が移り、第二順位の相続人(親)がいなければ、第三順位の相続人(兄弟姉妹)へ相続権が移ります。後でトラブルにならないように、相続放棄をする際には、そのことをおじにも伝えておきましょう。通常、多額の借金の相続の場合、相続人となるすべての人が相続放棄の手続きをすることになります。
※ 相続人全員が相続放棄すると相続人が存在しないことになります。このような場合は、被相続人の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになって、管理され清算されていくことになります。 そしてこの相続財産法人を管理して清算事務を行っていくのが、「相続財産管理人」です。相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている人または検察官が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。利害関係人とは通常、被相続人にお金を貸していた人などその財産に利害関係を持つ債権者のことをいいます。そして選任請求をする際は、誰々に管理人をお願いしたい、と推薦をすることもできますが、通常家庭裁判所が適任者と考える人(ほとんどが弁護士)を 選びます。
そしてこの相続財産法人を管理して清算事務を行っていくのが、「相続財産管理人」です。相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている人または検察官が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。利害関係人とは通常、被相続人にお金を貸していた人などその財産に利害関係を持つ債権者のことをいいます。そして選任請求をする際は、誰々に管理人をお願いしたい、と推薦をすることもできますが、通常家庭裁判所が適任者と考える人(ほとんどが弁護士)を 選びます。
相続開始から3か月過ぎてしまったら
問題になるのが、相続開始から3か月以上経つのを待ってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくるケースです。このような場合、相続人にとっては酷な結果になり、悪質な金融業者を増やすことになりかねません。そこで、相続人が借金のあることを知ることができない等の特別の事情がある場合には、相続開始から3か月以上経っていても、裁判所が相続放棄の申述を受け入れてくれることがあります。
【郡山市家庭裁判所】
郡山市麓山1-2-26 8時半から17時(土日休み)
TEL:024-932-5656

株式会社 コミットメント 福島県郡山市西ノ内2-5-29
TEL:024-936-4410 FAX:024-936-4412
営業時間:9時から18時
相談・査定無料です。
住宅・土地・アパート・駐車場などの売却や買取、管理、リフォーム、税金、ローンの組み方等不動産に関して、お気軽にお問い合わせ下さい。